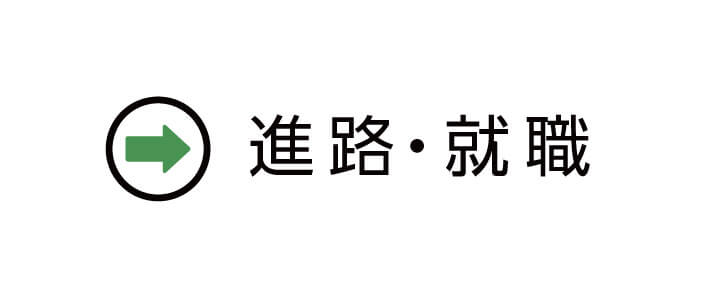より良い社会を構想するために
法学部長 館田 晶子
法学部での学びは人の営みのありとあらゆる領域に関わります。「私的なことは政治的なこと」という言葉があるように、法や政治は私たちの日常と地続きです。多様性は現代における重要なキーワードの一つですが、法学という学問には、社会が多様な人々によって構成されていることを前提に、利害関係を調整し、人々の尊厳を保ちながら秩序ある社会を維持していくために必要な知恵と技術が、凝縮されています。
社会は常に変化しており、21世紀に入ってその速度は加速しています。これまで社会の周辺に置かれてきた人々が権利主体として可視化されてきたのに伴い、マジョリティの視点で作られてきたこれまでの社会システムは、構造転換を迫られています。企業活動にコンプライアンス(法令遵守)が求められるのは最早常識となりました。科学技術の発達は法の世界にも新しい問題を提起します。最近では、チャットGPTをはじめとする生成系AI技術の一般化に伴い、著作権やプライバシー権、生成された内容に対する法的責任などが課題として指摘されています。
社会全体がダイナミックに変動している中で、大小様々な社会システムをより適切に機能させ、場合によっては大胆に見直していくにはどうしたらよいのか。それを考えるためには、確かな知識に裏打ちされた論理的かつ説得的な思考能力を磨くことが必要でしょう。
法学部では、そのような社会的要請に応えて、法律学や政治学を学ぶことを通じて法的思考力(リーガルマインド)と批判的思考力(クリティカル・シンキング)を身につけることを目指しています。
法学部は法律学科と政治学科の二つの学科からなっています。2年次学科選択制を採っており、1年次は法律学と政治学の両方について基礎的な科目を学びます。2年次に学科に分かれた後はそれぞれ専門的な学びを深めていくことになります。法律専門職を目指す人のために、法律学科では法曹養成プログラムと早期卒業制度を設けています。
また、法学部ではグローバル教育にも力を注いでいます。NPOインターンシップ、ニセコイングリッシュオンリーキャンプ、カナダ・レスブリッジ大留学、法政大学国内留学など、多様な学びの場を用意しています。人や物や情報が日常的に世界を駆け巡るようになった現在、国境を超えた社会のあり方が模索されています。現代社会における複雑な問題は、一つの国だけでは解決できません。法学的知見を持ったグローバルな人材は今後ますます求められていくことでしょう。
法や政治を考えることは、人々がより良く生きることのできる社会を考えることでもあります。皆さんと学べることを、法学部スタッフ一同、心待ちにしています。
法学部沿革
| 1964(昭和39)年 | 北海学園大学法学部1部法律学科、2部法律学科を開設。 |
|---|---|
| 1986(昭和61)年 | 北海学園大学大学院法学研究科法律学専攻修士課程を開設。 |
| 1992(平成 4)年 | 北海学園大学大学院法学研究科法律学専攻博士(後期)課程を開設。 |
| 1999(平成11)年 | 北海学園大学法学部1部政治学科、2部政治学科を開設。 |
| 2003(平成15)年 | 北海学園大学大学院法学研究科政治学専攻修士課程を開設。 |
| 2005(平成17)年 | 北海学園大学大学院法学研究科政治学専攻博士(後期)課程、北海学園大学大学院法務研究科(法科大学院)法務専攻専門学位課程を開設。 |